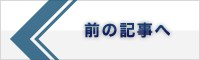政策より名称先行という「ためにする批判」・・・民進党、昨年末の「基本政策合意」をそのまま継承
2016年4月 6日 tag:
今回の新党結成にあたっては、安倍官邸と自民党、その広告塔と化した一部メディア、政治評論家等から「政策の議論もせず、先に名称を決めようとしている。政策なき合流は野合だ」との、悪意に満ちた「批判のための批判」が繰り返されました。
しかし、その「政策」は、結党にさかのぼること3か月以上前、昨年12月8日の民主、維新両党の党首会談で既に合意されていました。維新と民主が国会で統一会派を組むことを決めた時です。
それを知ってか知らずか、こうした批判を繰り返す方々の見識には、ただただあきれるばかりです。特に、一部の全国紙、著名な評論家までがこうした「ためにする批判」をしている姿をみると、何か、安倍官邸と特殊な関係があるのでは、と疑ってしまいます。
その「基本政策」ですが、3月29日に開かれた第一回のNC(次の内閣)で一言一句たがわず、民進党に引き継がれました。綱領から「30年代の原発ゼロ」が抜けた、後退したとの批判も受けましたが、それはこの「基本政策」の方に明確に「30年代の原発ゼロ」と明記していたので、そもそも綱領になじまない「年代つき」の表現を綱領らしい表現(「原発に頼らない社会」)に改めただけです。
民進党の「基本政策」は、後掲のとおりですが、その中で、旧維新の党らしい、その政策が盛り込まれた部分を以下に特記します。以前にも述べましたが、旧民主党がよく呑み込んでくれた、旧民主と旧維新の良いところが合体できた、その「合流効果」だと自負しています。
①安保法制については、単なる「廃案」だけでなく、旧民主党が昨年の国会で出せなかった「対案」を出すことを合意し、既に今国会に提出したこと(領域警備法、周辺事態法とPKO法の改正案)。
②「新陳代謝のある経済成長」を明記し、具体的には規制改革による新規参入や自由貿易の推進等による「持続的かつ実質的な経済成長を目指す」としたこと。
③「2030 年代の原発ゼロ」を明記し、再稼働については、国の責任を明確化し、責任ある避難計画が策定されることと、核廃棄物の最終処分場選定プロセスが開始されることを前提としたこと。
④「身を切る改革 」については、公務員に労働基本権を与え、自律的な労使交渉で給与等を決める、国家公務員については20年までに総人件費2割カットを目指すという、みんなの党以来の主張を盛り込み、既に今国会に法案を提出したこと。
さらに「議員定数の削減」や、「企業団体献金(パーティー券の企業団体による購入を含む。)の禁止」「文書通信交通滞在費の使途公開」を明記し、ほぼ100%の内容となったこと。
⑤同じく、みんな、維新以来の原点たる「地域主権改革」についても、「道州制への移行」を含め、明記されたこと。
以上のように、今回の新党結成、その肝である綱領や政策は、私、江田けんじの良心に照らしても、率直に受け入れられる内容となりました。「民進党」への名称変更を含め、心機一転、今後の課題は、この政策を党一丸となって実現すべく、責任政党として行動していくことだと考えています。
皆さんのご理解、ご支援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
(基本政策)
1. 現実的な外交安全保障
? 日米同盟を深化させるとともに、アジア太平洋地域との共生を実現し、国際社会の 平和と繁栄に貢献する。安全保障については、立憲主義と専守防衛を前提に、現実主義を貫く。
? 今般可決された安全保障法制については、憲法違反など問題のある部分をすべて白 紙化するとともに、我が国周辺における厳しい環境に対応できる法案を提出する。
? 核兵器廃絶、難民受け入れ、人道支援など、非軍事分野の国際貢献を積極的に行う。
2.立憲主義の確立
? 幅広い国民参加により、真の立憲主義を確立する。
? 日本国憲法の掲げる『国民主権、基本的人権の尊重、平和主義』の基本精神を具現 化するため、地方自治など時代の変化に対応した必要な条文の改正を目指す。
3. 新陳代謝のある経済成長
? 新規参入を拒む規制の改革によって、起業倍増を目標に新陳代謝を促し、持続的か つ実質的な経済成長を目指す。
? 経済連携協定によって自由貿易を推進する。ただし、個別具体的には、国益の観点 から内容を厳しくチェックし、その是非を判断する。
? 地域を支える中小企業の生産性向上のため、研究開発、人材、IT、デザインなど、 ソフト面への支援を強化する。
? 職業訓練とセーフティーネットを強化した上で、成長分野への人材移動を流動化す る。科学者、芸術家、起業家など、クリエイティブ人材の育成と集積を進める。必 要な海外からの人材は、計画的に認めていく。
? 同一労働同一賃金と長時間労働規制を実現し、働きがいのある社会を創る。
4. 「居場所と出番」のある共生社会
? 生活者、納税者、消費者、働く者の立場に立ち、社会の活力の根源である多様性を 認めあう格差の少ない寛容な社会を目指す。政治は社会的弱者のためにあるとの考 えを基本とする。
? 子どもと若者の支援や男女共同参画を進め、正社員で働くことができ、希望すれば 結婚し子どもを持つことができる「人口堅持社会」を目指す。
? 世代間公平に配慮しつつ、重点化と効率化によって、持続可能な社会保障制度を実 現する。
? 地方自治体、学校、NPO、企業、地域社会など、公共サービスの担い手を多様化し、 それぞれが十分に連携し合う社会を創る。
? 公務員について、能力や実績に基づく人事管理を進めるとともに、労働基本権を回 復して、労働条件を交渉で決める仕組みを構築する。労働基本権回復までの間は、 その代償措置である人事院勧告制度を尊重する。
5. 2030 年代の原発ゼロ
? 2030 年代原発稼働ゼロを実現するため、省エネを徹底するとともに、小規模分散電 源や自然エネルギーへのシフトを推進する。
? 原発再稼働については、国の責任を明確化し、責任ある避難計画が策定されること と、核廃棄物の最終処分場選定プロセスが開始されることを前提とする。
6. 身を切る改革
? 既得権益を排し、「官権政治」から「民権政治」へ転換する。
? 国民との約束である議員定数の削減を断行する。
? 企業団体献金(パーティー券の企業団体による購入を含む。)禁止と個人献金促進を 定める法律の制定を図る。また、透明性向上の観点から、文書通信交通滞在費の使 途を公開する法律と、国会議員関係政治団体の収支報告書を名寄せし、インターネ ットにより一括掲載することを義務付ける法律の制定を図る。
? 財政健全化推進法案に基づき、無駄な公共事業の削減と行政改革などを徹底するこ とで、2020 年度のプライマリーバランス黒字化を確実に達成する。
? 職員団体等との協議と合意を前提としつつ、国家公務員総人件費の2割を目標に、 その削減を目指す。
? 消費税10%への引き上げは、身を切る改革の前進と社会保障の充実を前提とする。
7. 地域主権改革
? 「権限・財源・人間」の東京一極集中を脱して、地域の創意工夫による自立を可能とす る地域主権社会を実現する。
? 基礎自治体の強化を図りつつ、道州制への移行を目指す。その際、それぞれの地域 の選択を尊重する。
? 国の出先機関をゼロベースで整理し、職員の地方移管を推進する。
? 税源移譲や国庫補助金の一括交付金化、地方交付税制度の見直しを含め、地方財政 制度を見直す。
Copyright(C) Kenji Eda All Rights Reserved.